
田植え
<田植え>
田植の時期は桜が咲く頃、4月~5月です。田植の頃はその年の豊作を願う「田植祭り」が各地で行われています。
出典: キノギフト
♦詳細
<田植えの時期は?>
GWになると1年で最も忙しくなる人たちも存在します。
百姓です!
ゴールデンウィークは田植え真っ盛りです。
お出かけする際には田んぼで頑張っている人たちを
眺めて見てあげてください。
田んぼに稲を植える作業はGWあたりですが、
田植えには他の作業もいっぱいあるので紹介します。
簡単に流して説明しますね。
米ができるまでの一連作業(田植えの手順)
①籾(もみ)の消毒
②筋蒔き(育苗)
③水回り、田んぼの手入れ
④田植え
⑤水回り
⑥稲刈り
⑦乾燥機、袋詰、出荷
米の収穫では田植えと稲刈りが一番目だった作業ですが、
影では地味で目立たない割に過酷な作業が多いです。
出典: 暮らしの楽得情報NAVI
①籾(もみ)の消毒
まず、籾の状態のコメがないと始まりません。
それをポリの容器に入れた消毒液につけます。
その後、完全に乾かします。
それが終わったら次の作業です。
②筋蒔き、育苗
この作業が田植え前の一大作業です。
籾から稲を出す(発芽)作業です。
ハウスの中で育てる百姓が多いですが、小屋の中などでやっている人たちもいるようです。
ハウスの地面には水を張るので、しっかりとビニルを地面にも貼る必要があります。
まず、580x280x28mmの黒い育苗器(プランター)にベト(土)と肥料と籾と水を混ぜあわせます。
それには専門のでっかい機械があります。
その育苗器をハウスの奥から並べていきます。
あまり外側に置くと外気が入っていて芽が出にくくなります。
3月の後半~4月の頭にやる作業なので、ハウスの中はサウナ状態でめちゃくちゃ暑いです。
並べ終わった筋(育苗器のもみ)にアルミシートをかけて温度をキープします。
そして用水路や川から水を引き、ハウスの中を浅いプール状にします。
それから田植えの時期までの約一ヶ月間はハウス管理が必要です。
朝、夕にハウスの脇を少し開けてやって換気してあげないと稲が熱くて死んでしまいます。
最近では電気で稲を育てる育苗機もあるようですので気になる方は調べてみるといいかもしれません。
③水回り、田んぼの手入れ
田んぼは水を引かないといけないので、
水回りの手入れが必要になります。
用水路の掃除
田んぼに水を入れる配管
田んぼから水を捨てる配管
あぜのチェック
しろかき
ゴミ取り
田植え前には必ずやっておく作業です。
田んぼの縁となる「あぜ」をチェックしながら配管のチェックもしないといけません。
あぜから水が洩れるようであればベトで固めて上げる必要があります。
それから、田植え前にしろかきという田んぼをならす作業があります。
トラクターを使って田んぼを平にします。
代掻きをうまい人がやるか、下手な人がやるかで田植えのしやすさに変化があります。
そして田植え直前には田んぼに水を入れます。
代掻きで出たゴミなどが浮いてくるので取ってあげます。
取らないと田植機に絡まったりするのでなるべく綺麗にしてから、田植えに望みましょう。
④田植え
ついに田植えです。
5月くらいになれば育苗器の苗も10センチ前後の長さになっています。
それをトラックの2台に組み立てた専用の棚に入るだけ入れて、田んぼに直行です。
田植機に苗を補充して田植え開始です。
ちゃんと端っこまで植えてくれます。
あまりあぜの近くに植えすぎると
刈り取れなくなります。
田植機の後ろです。
田植機がうまい具合に苗を2~3本くらい取って
植えてくれる仕組みになっています。
田植機が植えられなかったところや、深くて値付け
できなかったところなどは手植えで補います。
雨の日の田植えは?
あまりに多雨だったりすると、田んぼの水かさが増えて値付けが難しくなります。
肥料も濡れて固まったりします。
なるべく晴れてる日にやりたいです。
⑤水回り管理
田植えをしてからのほうが大変だったりします。
雨や風で稲が倒れていないかとか?
水の温度などを調整するためにも、田んぼの水の入れ替えなどをしなければいけません。
毎日のチェックが必要なのでかなり大変です。
特に田んぼが多い人はかなり過酷です。
ある程度の長さまで稲が育ってしまえば雑草のように強くなるので大丈夫です。
問題は除草剤撒きや虫バスター的なものを巻かないといけないのも大変です。
1年1回のものもあれば、年数回撒かないといけないものもあります。
⑥稲刈り
稲刈りも大変です!
稲が湿っていたりすると、稲刈り機の中で詰まったりします。
田んぼに豆木などが生えていると鎌で切ってあげないと田植機につまります。
田んぼから刈ったもみをトラック載せかえて、乾燥機まで運びます。
かなりでかい煙突みたいな乾燥機でもみを1日かけて乾かします。
それからもみを排除する機械(うす)にかけてようやく袋詰ができます。
袋に詰めた米をパレットに乗せて出荷、または冷蔵庫に保管します。
かなりざっと米の収穫の流れを説明しました。
一つ一つの作業が、自然を相手だったりするので結構大変だったりします。
機械が壊れた時も何もできない事が多いです。
しかも稲刈り時期になると、爆弾低気圧がきたりしてハウスごと持って行かれたという時もありました。
田植えや稲刈りは目立つ作業ですが、他の地味な作業のほうが大変です。
出典: 暮らしの楽得情報NAVI
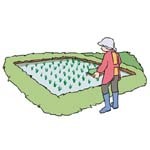
♦豆知識
<田植えのを始める時期はいつから?その手順は??>
お米の作り方は時期や地域により様々ありますが、一番手軽な方法をご紹介します。
田植えの手順はまず
”種もみ”の準備から始まります。
4月上旬に種もみを塩水に浸けて、よい種を選び出します。
中がしっかりと、つまった重くてよい種を選ぶ方法です。
塩水に沈んだ種もみを使うのですが、その後病気にならない様に消毒を施し芽が出やすくなる様に水に浸します。
4月中旬に育苗箱に肥料を混ぜた土を入れ、種もみを撒いて薄く土をかけます。
種もみを田んぼへ直接撒いてしまう方法もありますが、多くの田植えは10数センチに育った苗を田んぼに植え付ける方法が主流です。
4月下旬に育成箱で育っている苗を丈夫に育て温度管理や水を与えたりし大切に育てます。
それと同時に4月下旬~5月上旬に肥料と土が混ざる様に田起こしをし、ムラなく植えられる様に代かきを実施。
田に水を張りながら行います。
そしていよいよ5月中旬に田植えを行います。
<田植えの苗の植え方のコツは?手作業では?>
いよいよ苗を植える場合、個人で行う場合には手作業になります。
広さにもよりますが、それでも腰をかがめて行う為なかなかの重労働です。
始めに升目を書いておく事が大事です。
糸をピンと張りガイド線を真っすぐに引きます。
農耕道具に熊手を大きくした様な感じのものがあるので
それを用意すると一遍にいくつもの線が書けるので便利です。
株間をあけると稲が太陽をたくさん浴びてすくすくと大きく育ち、風通しもよくなるので
病気にもなりにくいという利点があります。
ギュウギュウと詰め込まない様に升目を書く重要性が出て来ます。
苗は一定の間隔で1~2本ほど線と線が交わったところに植え付ける様に。
植え終わるとスカスカなのですが、育って来るとその違いがわかります。
<田植えを行うときの服装のポイントは?>
学校の授業などで近所の農家さんから田んぼを借りて田植えの授業を行うといった事もある様ですね。
田植えの際の服装は『汚れても気にしない服』
これに尽きます!
泥だらけになりますし、あやまって泥から足が抜けなくなって危うくバッチャーン!
と尻もちをついた・・・なんてことはあると想定します。
ジャージなど動きやすく、ズボンもたくし上げる事が出来るもの。
始めからハーフパンツなどで出かけてもよいと思います。
長靴は抜けなくなったり、深さによっては意味を成さないので素足で入るのに抵抗がある場合には、汚れてもいい靴下を履いて田んぼに入りましょう。
陽射しが強い日もありますので、帽子や汗を拭うタオルなど・・・
必要とあれば着替えの準備もお忘れなく!
出典: トレンド豆知識
