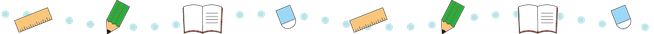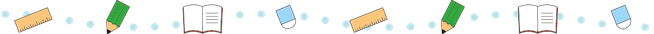
年中行事の役割
日本では、毎日どこかで祭りが行われているといってもよいぐらい、多くの年中行事や祭りがあります。
その多くは、農耕や漁労で生きてきた日本人が自然を畏れ、その恵みに感謝するために行ってきたものです。
★春には豊作を願って山から田の神を迎え、
★夏には稲の生長のために雨乞いをし、害虫を追い払う虫送りをして、
★秋には稲刈りを済ませると、感謝を捧げて田の神を山に送り返しました。
★冬には、1年の平安と豊作を祈る正月の一連の行事があります。
このように、かつての日本人の生活は、感謝と祈りに満ちたものだったといってもいいでしよう。
お彼岸やお盆などの先祖の祭りも重要でした。
先祖は子孫を見守るために戻ってくると考えられていたからです。
先祖の祭りは、人はひとりでは生きていけないことや、過去から未来へとつながる命の流れの中に自分もいることを気づかせてくれます。
また、花見や紅葉狩りなどの四季おりおりの遊びは、今も昔も変わらず、日常生活にアクセントをつけてくれます。
娯楽の乏しかった頃は、今よりも、もっと楽しみだったに違いありません。
昔の人は、生産や生活のため、季節の変化を注意深く見つめてきました。
暦はその集大成であり、年中行事も暦に従って行われます。
現代の生活は暦とはあまり関係がなくなっていますが、年中行事は季節感を代表し、生活にリズムをつけるものとして、欠かせないものになっているといえるでしょう。
年中行事とふたつの暦
農耕や漁労を行うには、正確な暦を作って季節の移り変わりを知ることが重要でした。
現在の「太陽暦」が導入されるまで、1200年間にわたって使われてきたのが、旧暦といわれる「太陰太陽暦」です。
現在の暦では、立春が真冬にきたり、七夕が梅雨のさなかだったり、季節感と年中行事にずれを感じることがあります。
これは、太陽暦が新暦として導入された、明治5年12月3日が明治6年(1873年)1月1日とされたことにあります。
つまり、このときに暦が1ヵ月早まったわけです。
また、行事の中には、お盆のように地方によっては、今でも月遅れで行われているものもあります。
年中行事を考えるときには、新暦と旧暦の2種類の暦があることを頭に置いておくとわかりやすいでしよう。
太陰暦
太陰とは月のことで、太陰暦は新月から新月までの29日、あるいは30日を1ヵ月としたものです。
1年は約354日となり、実際の季節の推移と暦の月日にズレが生じます。
太陰太陽暦(旧暦)
太陰暦をベースとして、季節と暦のズレを解消するために、2~3年に1度、閏月(うるうづき)を入れるようにしたものです。
日付は月と同調し、毎月朔日(さくじつ)、すなわち1日が新月になり、15日は満月になります。
日本の太陰太陽暦は、中国の黄河中・下流域で殷の時代に作られたもので、飛鳥時代に伝来しました。
閏月のほかに、暦と季節感のズレを調整するものには、太陽の動きに合わせた「二十四節気」が取り入れられました。
しかし、これも中国で作られたものなので、日本の季節感とずれているところがあります。
それを補うために「雑節」が用いられました。
太陽暦(新暦)
地球が太陽のまわりを365.2422日かけて1回転する周期を、1年としたものです。
4年に1日のズレが生じるため、閏年で誤差を調節しています。
季節の進行には忠実ですが、月の巡りに関係がある潮や動植物の変化がつかみにくいという欠点があります。
出典: ワイドバラエティー